言語相対論からチョムスキーの普遍文法論へ
言語が異なれば、物事の捉え方や把握の仕方も異なる———
このような考え方は、「言語相対論」と呼ばれる。
19世紀から20世紀にかけて西欧諸国が植民地を拡大する中で、非西欧文明との接触が進み、世界の多様な言語への関心が高まった。これは、言語の多様性に対する視野が大きく広がった時代であったと言える。
この時期の言語学では、さまざまな民族の言語を比較することで、言語によって物事の表現の仕方が異なり、それが認識の仕方にも影響を及ぼすことが明らかにされた。この発見を契機に、各言語の固有の法則や形式が、それ自体として価値のあるものと評価されるようになっていく。それぞれの言語には独自の観点や論理があるという、言語相対論的な考え方が一般化していったのである。
いくつか具体例を挙げると、まずアメリカでは、B.L.ウォーフの研究がある。彼はネイティブ・アメリカンの言語を研究し、実証的な知見に基づいて、言語ごとに物の認識の仕方が異なることを示した。
また、ドイツでは意味論学派の研究が挙げられる。意味論学派は語彙の意味解釈を通じて、各言語に固有の認識方法が存在することを理念的に主張した。内在的な意味分析の成果として、言語相対論の考え方が支持されていた。
このように、20世紀前半の言語学界では、言語相対論が主流を占めていた。
しかしこの言語相対論に真っ向から異議を唱える主張が、大戦後に突如として現れる。それが、チョムスキーによる生成文法である。彼がこの理論を発表したのは1957年であり、1960年代を通じて言語学界に多大な影響を及ぼすこととなった。
生得的な文法の存在を証明することの時代的限界
チョムスキーは、言語に文法が存在し、それが規則的に運用される根拠を、人間の生得的な知識に求めた。
世界には多種多様な言語が存在しているが、一見するとそれぞれ独自に成立しているように見える言語形式も、実は共通の普遍的な構造を基底に持ち、それが具体的な運用の段階で多様なかたちに展開している――これがチョムスキーの基本的な発想であった。
しかし、「生得的知識」という人間の脳内に存在すると仮定されるものを、実証的に証明する手段は、当時はまだ確立されていなかった。1960年代当時は、MRIやPETといった脳科学の研究技術が未発達であり、脳科学的知見をほとんど用いずに生成文法論が展開された。そのため、「人間は文法的知識を先天的に備えている」というこの革新的かつ一見奇異な言語観は、熱烈な支持を集める一方で、多くの批判も招くこととなった。
当時の生成文法論において採用された方法論は、主に仮説の提示とその検証という、極めて伝統的な学問的方法であった。すなわち、生得的な知識とされる文法規則を理論的仮説として提示し、それを他言語に適用して帰納的に妥当性を検証するという手法が取られていた。チョムスキー以降、多くの言語学者がこの方法論に基づいて研究を行っていた。
ただし、このような方法論によって証明できるのは、あくまで理論仮説としての妥当性にとどまり、その実在そのものを証明することはできなかった。言い換えれば、「生得的知識」とされるものはあくまで理論仮説であり、それ以上のものではなかったのである。
ところが、1980年代以降、MRIを用いた脳波測定の技術が一般化し、脳科学は飛躍的な発展を遂げる。その結果、言語の認知や処理に関する多様な知見がもたらされるようになった。こうした脳科学の進展を受けて、生成文法の理論を脳科学の観点から裏づけようとする試みも行われるようになる。生成文法を検証するための新たな方法論が登場したのである。
これは、チョムスキーが提唱した「生得的知識」の実在を、実証的に立証しようとする取り組みであるといえる。生成文法論は、ここに至って新たな時代を迎えることとなった。
脳科学の実証研究による証明の試み
では現在、脳科学は人間の生得的な言語知識にどこまで迫ることができているのだろうか。
現時点で脳科学が明らかにしている主な成果は、次の二点である。それは、①脳の機能局在、②各機能の独立性(モジュール仮説)である。
まず、脳は言語情報を「統語(文法構造)」「意味」「音韻(音の構造)」といった異なる要素に分け、それぞれを異なる部位で処理していることが分かっている。このように、特定の機能が特定の脳領域に対応しているという考え方を「機能局在」と呼ぶ。これは、言語の脳科学的理解における基本的な枠組みである。
さらに、この知見に基づいて、人間の言語能力は、複数の独立した情報処理機能(モジュール)が連携することで成り立っているという「モジュール仮説」が提唱されている。
たとえば、「話す」「聞く」「書く」「読む」といった言語の4技能は、それぞれ脳の異なる領域で処理されており、各機能には一定の自律性が認められている。
ここで脳科学が証明しているのは、人間に普遍的な言語能力が「身体的・物理的な脳の機能」として備わっているという点にとどまる。しかし、チョムスキーが目指していたのは、すべての言語に共通する「普遍文法」という、統一的な処理原理=言語知識としての法則の存在を示すことだった。
つまり、脳というハードウェア(hardware)の普遍性ではなく、言語の情報処理システム(ソフトウェア/software)としての普遍性こそが、チョムスキーの問題意識だったのである。
脳科学の限界
チョムスキーは、幼児が必ずしも理想的とは言えない言語環境から、正しい文法知識を獲得できるのは、行動主義の立場からは説明できないと指摘していた。これを「プラトンの問題」と呼ぶ。
たとえば、幼児が接する発話には、言い間違いや言い淀み、文法的に誤った表現(破格文)などが多く含まれている。このように不完全で曖昧な言語環境の中で、何が正しく、何が誤っているかを幼児自身が見分けるのは困難である。なぜなら、「正しさ」そのものを示すためにも、やはり言語が必要だからだ。
したがって、仮に与えられる情報が不確実なものでしかないとすれば、幼児が完全な文法を獲得することは原理的に不可能ということになる。しかし実際には、幼児はこのような不確実な状況を乗り越え、言語を正確に習得している。チョムスキーは、この現象を説明するために「人間は文法に関する知識を生まれながらに備えている」と主張した。
この立場に立てば、人間の脳には、「話す・聞く・読む・書く」といった言語を運用するための普遍的な機能(身体的、物理的なもの)の他に、統語論・意味論・音韻論に関する普遍的な知識(情報処理的なもの)も備わっていなければならない、ということになる。
だが、現在の脳科学が解明した機能局在とモジュール仮説は、「言語処理の際に、脳の特定の部位が特定の役割を果たす」という考え方であり、脳の物理的構造や働きに関する説明である。これは、人間に共通する身体的な機能の普遍性を示しているに過ぎない。これは、文法や言語規則といった言語情報処理のアルゴリズム的な普遍性を証明するものではない。
つまり、機能局在が示すのは、生物学的な「機能」や「能力」の普遍性であり、言語処理における情報処理的な普遍性とは本質的に異なる概念である。
実際、どのような言語にも文法や規則は存在し、人々は日常的にそれを用いて正しく言葉を理解し、発話している。このような社会的事実をふまえれば、人間が統語構造や意味、音韻といった要素を正しく処理する能力を普遍的かつ生得的に持っていると考えるのは自然なことである。
しかし、問題はその「知識」がどのようなものなのかが、まったく明らかになっていない点にある。人間が言語を適切に使っているという事実は普遍的であっても、その背後にある処理の法則が本当にすべての言語で共通しているのかどうかは、いまだ不明である。多様な言語の全てが基づいている深層的な規則や普遍的知識については、脳科学からは何も分かっていないのである。
言語ごとに異なる多様な文法が、単一の普遍的な法則で処理できるのか。そして、もし可能だとすれば、それはどのような形態の「知識」なのか——この問いはいまだ解かれていない。
チョムスキーの生成文法は、そのような普遍的知識(文法)が存在するとした上で、構築された理論的仮説である。
現代の脳科学は、脳の物理的な機能に関しては大きく進展しているが、統語論・意味論・音韻論に関する普遍的な規則の存在や、それが「知識」として脳内にあるのかどうかについては、証明に至っていない。そもそも、言語情報を処理する法則が、どのような形式で、どのような種類の知識なのかさえ、いまだ明確にされていないのが現状である。
もし脳科学が脳の情報処理規則を明らかにしようとするならば、シナプス間の結合様式といった微細なレベルの神経活動を解明する必要があるだろう。
普遍性の意味を取り違える誤り
チョムスキーの「人間は文法に関する知識を生得的に持つ」という主張と、現代の脳科学が証明しつつあることとの間には、依然として大きな隔たりがある。それにもかかわらず、両者を安易に結びつけて論じる議論が少なくない。
言語処理が脳内の「どこで」「なにを」行っているか、ということは、現代の脳科学でかなりの範囲が証明できつつある。
しかし、「どのような規則」によって多様な形で現れる言語を統一的に処理しているのか、あるいは文法や言葉の意味を解釈しているのか、ということは全く未知の領域だ。それがどのような種類の知識であるのかさえ分かっていない。
言語と脳科学は、ともに目覚ましい発展を遂げているが、「何が証明されていて、何が証明されていないのか」を明確に見極めることが重要である。さもなければ、「言語の普遍性」という概念そのものを誤解してしまう恐れがある。
なぜなら、どの言語であっても脳内の普遍的な機能によって処理されるという脳科学の示唆と、あらゆる言語規則が生得的な知識から演繹されるというチョムスキーの主張とでは、「普遍性」という言葉の意味そのものが異なっているからである。
まとめとして
脳科学が明らかにした機能局在や各機能の独立性は、「言語を運用するための機能」が人間に共通していること、つまり身体的な普遍性を示したにすぎない。これらは、すべての言語に共通する文法的な法則や統一的な処理知識の存在を証明したわけではない。
文法などの言語処理が他の認知機能とは独立して、脳内の特定のモジュールで行われるということは、脳科学の研究によって徐々に裏付けられている。しかし、こうした知見を根拠に、チョムスキーのいう普遍文法の存在を安易に結論づけることはできない。
チョムスキー理論の正しさを検証するには、多様な言語規則を共通の法則で処理できる知識が本当に存在するのか、それがどのような性質を持ち、脳がどのように処理しているのかを明らかにする必要がある。それには、ニューロンの働きから、そのアルゴリズムを解明する必要があるだろう。
チョムスキー派の研究者たちは、生得的な文法知識の存在を前提としているが、脳科学はまだその実証には至っていない。まずは「言語の普遍性」という言葉の意味を見直すことが求められる。そうしなければ、脳科学は言語における機能の普遍性の証明以上の段階に進むことができないだろう。
こうした状況は、私たちにあらためて「言語とは何か」という根本的かつ哲学的な問いを突きつけている。
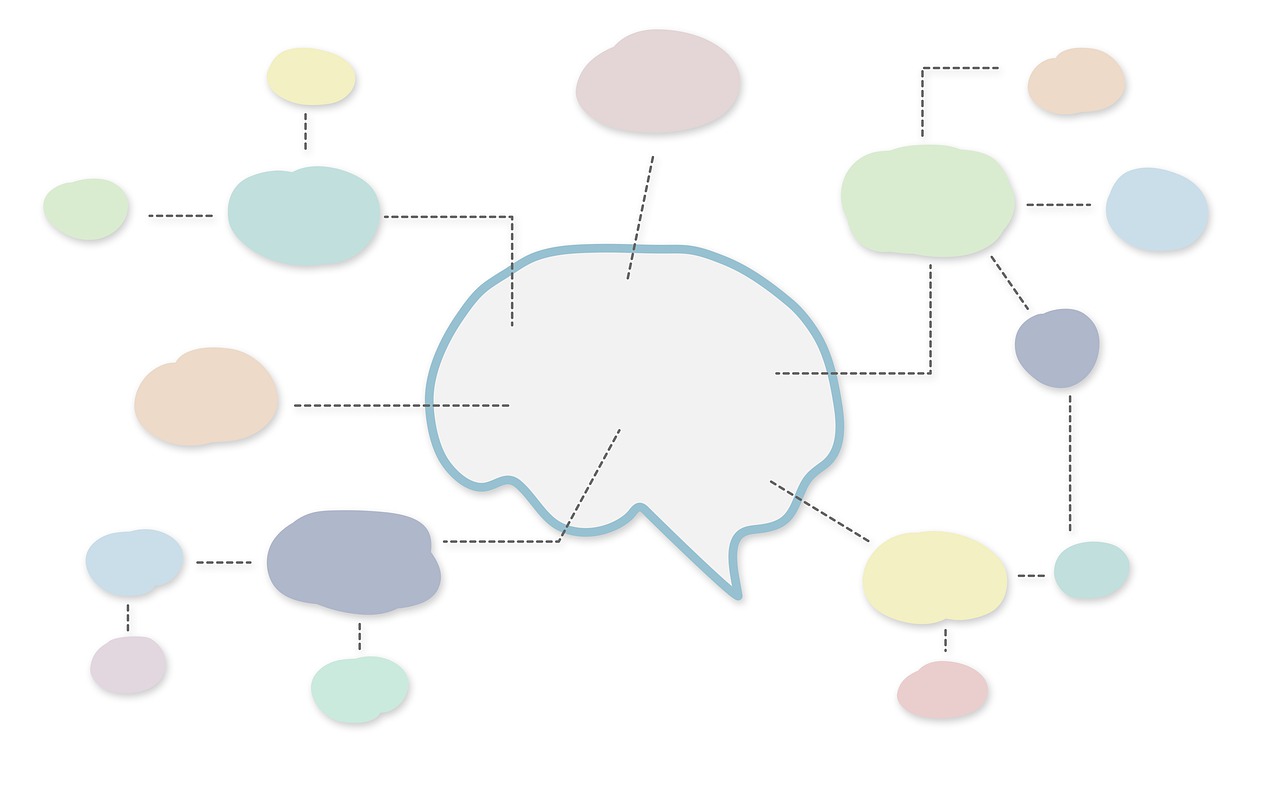


コメント