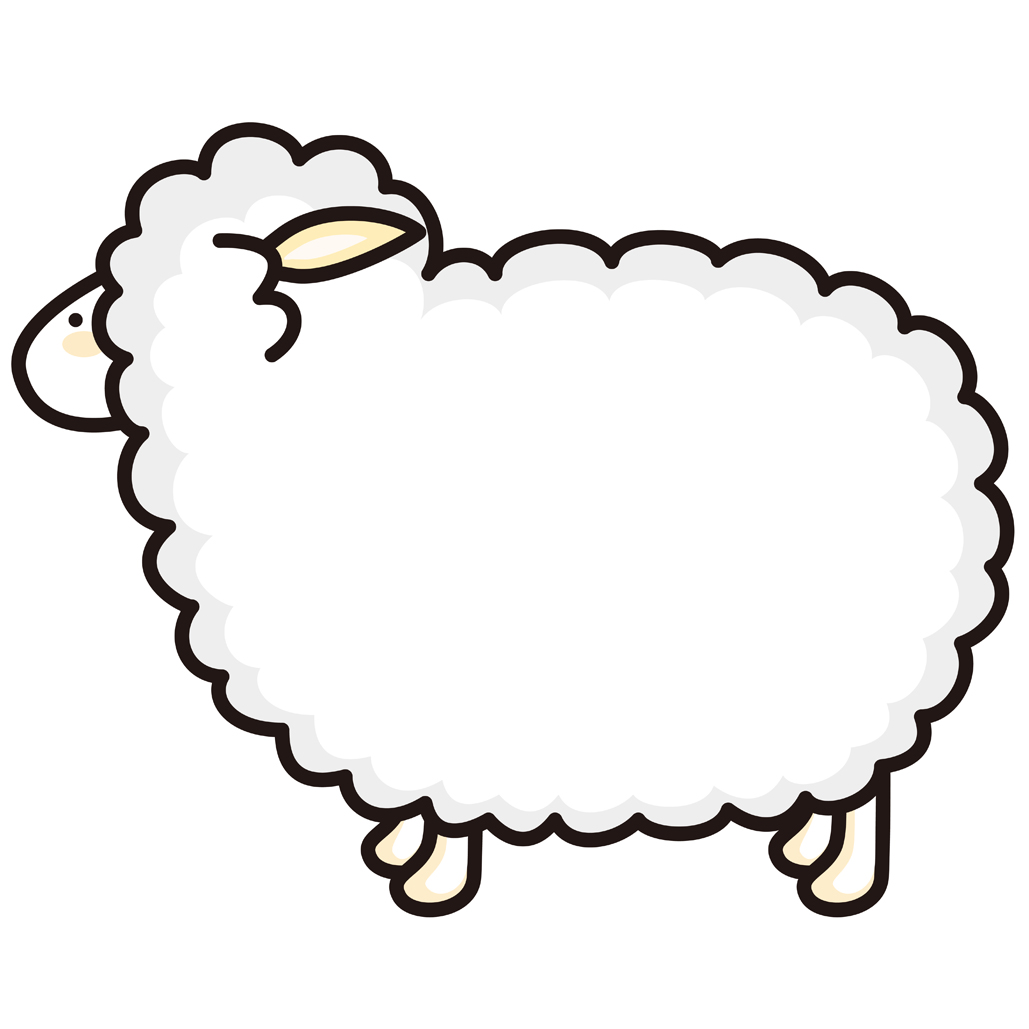加賀野井秀一『日本語を叱る!』(2006)
タコツボ化する日本語
2006年刊行。
前作『日本語の復権』と同じく、「甘やかされた日本語」に喝を入れ、日本語の表現能力を鍛え直そうというもの。前作よりも読みやすく、論旨も掴みやすくなった。
日本人は、相手の察する能力に依存して、表現を短縮したり、曖昧にしたままで意思の疎通を行ってしまう。気心の知れた間柄では、論理的で冗長な表現よりも、むしろ示唆に留めただけの表現の方が、気の利いた言い方として受け止められたりする。
しかし、その結果、日本語の表現能力は著しく低下し、限られた仲間内だけで理解が成立すればよい、といったタコツボ化を引き起こしている。
日本語は特に、表現を簡略化しやすい構造を持っているので、話者が意識的に論理的な表現を心がけないと、この傾向をいっそう強めてしまう。
論理的で明確な表現の重要性が失われ、世代間、地域間、民族間を横断するコミュニケーションが欠落していく現代の日本社会。。。著者は、日本語の歴史から検証して、日本語を鍛え直すことで、日本語表現の新たな可能性を探っている。
二重言語としての日本語
日本語の歴史を振り返ると、日本語の形成と特質に大きな影響を与えたのはやはり、4世紀頃の漢字の伝来だったと考えられる。日本語は類型的には、膠着語に分類され、実質的な意味を表す自立語に、文法関係を示す付属語が後に続いていく構造を持っている。自立語は詞、付属語は辞と呼ばれ、この二つの要素からなる日本語の特徴は、詞辞構造と呼ばれる。
日本語は、この詞の部分に概念化と分析力の強い漢語が入り込んで、それを日本語の辞が包み込むという発展の仕方をした。詞は事象の概念化、辞は文章の論理展開を主に担っているといえる。日本語はこの概念化と論理展開が、全く別の出自をもつ言語によって担われているのが特徴で、両者の間に断裂が生じている。
これは欧米の言語と比べてみると良く分かる。欧米の言語は、一つの単語が名詞から形容詞、動詞へと品詞転換していくことが容易で、概念化と論理展開の間が一直線でつながっている。漢語が主に名詞、大和言葉が主に文法要素と述語、という形を取る日本語との違いは明らかだ。
ここから日本語の二重言語としての特質が現れてくる。二重言語とは、概念化と論理展開の間に断絶があり、それぞれ別系統の言語によって担われている状況を指した言葉だ。日本語は概念化と論理展開がそれぞれ自立した別の体系を作り上げてしまっているため、どちらか片方だけでも明確であれば、十分文章としての体裁が整ってしまう。たとえば、「てにをは」の論理がしっかり出来ていれば、文の内実を示す名詞の部分が曖昧でも、「なんとなく分かったような」文章が出来上がってしまうのだ。
文章の詞の部分をやたらと難解な漢語で埋め尽くせば、「なんとなく」高尚で有難い文になる。そして、今では、この詞の部分は、漢語からカタカナ語へと取って代わられているだけで、カタカナ語を連発すれば「なんとなく」カッコイイ文になる。
日本語は主に物事や事象を概念化することに関して、外来語の力を利用してきた。それは、日本語の概念化の力が、非常に弱いということでもある。言葉の意味の内実を理解しないまま、その言葉が持つ雰囲気のみで使用してしまう大量の漢語、カタカナ語が溢れる結果となっている。
このような言語文化を招いた二重言語としての日本語の性格をよく踏まえた上で、日本語を如何に開かれた言語にしていくかがこれからの課題だ。
論理的な表現を目指して
このように日本語の歴史から日本語の問題点を洗い出していくと、巷に溢れる昨今の日本語論がいかに底の浅いものかがよく分かる。メディアがよく取り上げる日本語の問題というのは、そのほとんどが「正しい日本語の使い方」についてだ。
たとえば「的を得る」といった誤用を指摘するものや、敬語の正しい使い方、適切な表現の紹介といったことに留まっている。そして、「正しい使い方」というのは、時代によって変化するといった陳腐な相対主義で最後に話を濁してしまうのが、たいていの場合のオチだろう。
これらの現れてはすぐに消えていく「日本語ぶーむ」を著者は日本語に関する擬似問題として斬って捨てている。
日本語に関する本当の問題とは、詞の部分だけが浮き上がってしまって言葉の内実を忘れていることであり、その一方で、概念化が希薄で物事を客体視できないため、表現が自分の感情や感性に寄り添いすぎてしまうことにある。感情過多で論理性が曖昧になり、雰囲気だけの言葉で内実が疎かになっている。その結果、日本語は、その場だけで、あるいは内輪だけで理解できればよいという完全なタコツボ化状態にある。
このタコツボ化を改め、他者にも開かれた日本語にしていくことこそが本当の問題だ。
著者は、開かれた日本語にしていくためには、翻訳という発想が鍵になると述べている。翻訳とは、何も異なる言語間にのみ行われるものではなく、同じ言語の中においても世代間、地域間、時代差、性差、民族差など、すべての差異の間でも行われうるものだ。
常に言い換えや別表現の可能性を探ることで、その文章が本来何を伝えようとしていたのかが、より明確になっていく。つまり、さまざまな表現を比較することで、文章を分析する能力は向上していくことができる。この「翻訳の思想」が、日本語を開かれた言語として立て直していく上で、最も必要とされているものなのだ。
雰囲気だけに惑わされる日本語、タコツボ化する日本語を叱りつけ、日本語の本来の可能性を探ることこそ、本当の日本語の問題なのだろう。